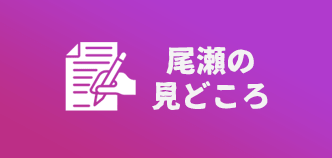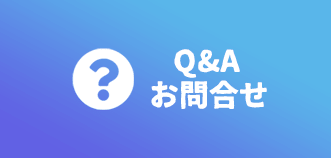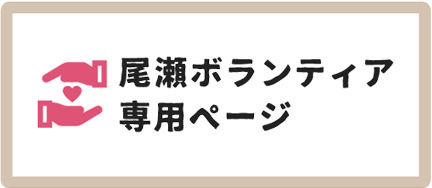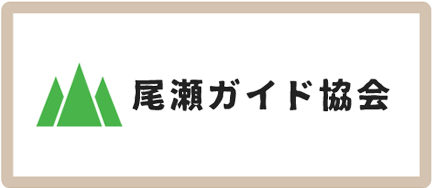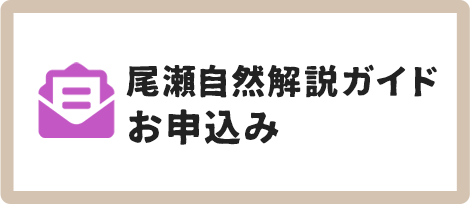- 尾瀬沼ビジターセンターブログ
- 2021.08.08
2021年8月8日-尾瀬沼ビジターセンターより(アサギマダラ飛来)
==================================================================
尾瀬への入山にあたってはこちらの注意事項をご確認ください。
また、環境省尾瀬沼ビジターセンターは、基本的な感染予防対策を実施したうえで、一部開館しています。
詳細はこちらをご覧ください。
==================================================================
■天気:曇り一時雨
■気温:18.3℃(9時)25.7℃(昨日の最高気温)16.1℃(今日の最低気温)
ブログをご覧の皆様こんにちは。
朝方の小雨はあがりましたが湿り気の多い曇り空の尾瀬沼周辺、燧ヶ岳の姿は低い雲に包まれ全く望めません。
台風10号が関東南部を通過していますが、幸い尾瀬沼周辺は強い風が吹くこともなく今のところ静かです。
昨日、渡りをする蝶、アサギマダラが尾瀬沼ビジターセンターの周りに1頭飛来しました。
ヤナギラン、マルバダケブキで吸蜜、地面に降りて吸水している姿を撮影することができました。
【ヤナギランで吸蜜するアサギマダラ】

アサギマダラは独特のふわふわした感じの飛翔、光の加減でメタリックの浅黄色に光る翅が素敵です。
【マルバダケブキで吸蜜するアサギマダラ】

このアサギマダラは後翅に黒班(性標)が見られるのでオスだと分かります。
【地面で吸水するアサギマダラ】

アサギマダラはヒヨドリバナ、ヨツバヒヨドリ、フジバカマ、ソバなどを好んで吸蜜に訪れます。
吸蜜中は数センチまで寄っても逃げないので比較的撮影も容易な蝶です。機会があればぜひ撮影にチャレンジしてみて下さい。
【ヒオドシチョウ(7月11日撮影)】

木道上で休んでいたヒオドシチョウ。アサギマダラと同じタテハチョウ科に属します。
成虫で越冬し春先に交尾し次世代に命を繫ぎ、夏前に次世代が羽化します。
ヒオドシの名は戦国時代の武具「緋縅」、緋[ひ]色(=燃えるような赤色)の縅[おどし](=鎧)に由来します。
始めて見たときに燃えるような緋色にワクワクしたのを今でも思い出します。
【ウラギンヒョウモン(7月11日撮影)】

ノアザミにはヒョウモン[豹紋]チョウ類がよく吸蜜に訪れます。
ヒョウモンチョウ類は特徴をしっかりつかまないと同定が難しく毎回図鑑のお世話になります。
【ミドリヒョウモン(7月16日撮影)】

ヒョウモンチョウ類はスミレ科の植物を食草として幼虫が育ちます。大江湿原にもオオタチツボスミレやツボスミレなど食草となるスミレ類が多くありますので、ここでの発生も考えられます。
アサギマダラの様に海を渡ってくる生命力、ヒョウモンチョウ類に限りませんが毎年尾瀬の厳しい冬を乗り越えて命をつなぐ生命力、その凄さにいつも敬服します。
最後に、体調に不安がある方や、自ら安全確保を行うことが難しい方の尾瀬への入山は控えてください。
くれぐれも冷静な判断をお願いいたします。
尾瀬沼ビジターセンター